今月のフィールド ~2014年10月 荒雄川~(動画あり)|フライフィッシング データバンク
「今月のフィールド」2014年10月は、宮城県の荒雄川をピックアップし、動画とともに紹介
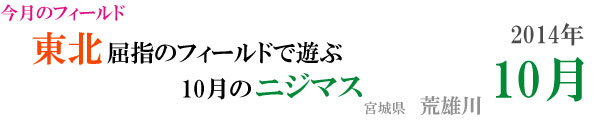
 宮城県の鬼首(おにこうべ)高原を流れる東北屈指の人気フィールド・荒雄川。
宮城県の鬼首(おにこうべ)高原を流れる東北屈指の人気フィールド・荒雄川。シーズン中には対象魚が異なる2種類のC&R区間が設定され、コンディションの良い大型魚が釣れることから、東北だけでなく首都圏からやってくるフライマンも多い。下流側のA区間はニジマス。上流側に設定されるB区間はヤマメとイワナのフィールドだ。
このうちA区間は、他の区間が禁漁となっている10月1日から11月30日までの期間、「特別遊魚区域」として毎年開放されている。
禁漁期間にフライフィッシングを楽しめる数少ない自然河川のひとつだ。
 2014年のレギュレーションは、区間最下流部のみエサ釣り区間で、残りはルアー・フライ区間。全区間がC&Rとなっている。対象魚はニジマスだ。
2014年のレギュレーションは、区間最下流部のみエサ釣り区間で、残りはルアー・フライ区間。全区間がC&Rとなっている。対象魚はニジマスだ。ニジマスは堰堤下に
フィールドの雰囲気は渓流というよりも、本流的という感じなのだが、減水気味の日が多くなる10月の流れは、写真で見る印象よりも実際には浅い箇所が多い。遡行にはさほど苦労せずに済む。
荒雄川に限った話ではないが、この時期にドライフライに反応してくれるニジマスは、流れのどこにでもいるわけではない。ニジマスのついているポイントを見つけることが釣果を左右する大きな要因となるのだ。
 取材は2014年9月。
取材は2014年9月。荒雄川は、ゆったりフラットなトロ瀬が、広い川幅いっぱいに流れている箇所が多いが、この日はそうしたポイントにニジマスの姿は見当たらなかった。
荒雄川のC&R区間内では低い堰堤が次々に姿を現すのだが、ニジマスはその堰堤下流側、流れのスジがハッキリしていて水深もあるポイントに集まっていたのだ。
この日は薄曇り。時折小雨がぱらつく。午前8時の水温は13度。適水温。ドライフライでのフライフィッシングには悪くない条件で期待していいはずだ。
ティペットには大きめのフライが結ばれている。大型魚は大きめのフライに出てくるだろう、という狙いだ。
 ところがこの日のニジマスは、大き目のドライフライに反応することはただの一度もなかった。
ところがこの日のニジマスは、大き目のドライフライに反応することはただの一度もなかった。#18のフライに入れ食い
気を取り直してあたりを観察すると、流下こそ確認できないもののミッジに混じって小型のメイフライが飛んでいる。
フライを#18、ストリップドピーコックを使ったクイルボディのフローティングニンフに交換して仕切り直し。
するとどうだろう。今度は、グッドサイズのニジマスが次々にフライに飛び出してくるのだ。中には遠目の位置から横飛びでジャンプしながらフライに喰い付いてくるヤツさえいる。入れ食い状態といっていい。
 試しにフライを#18の羽アリパターンに交換してみるが、やはり入れ食い。
試しにフライを#18の羽アリパターンに交換してみるが、やはり入れ食い。#14では完璧に無視される。#16にも反応は渋い。
だが#18以下であれば、パターンを問わずにニジマスは驚くほどの反応を見せてくれた。
この日の荒雄川のニジマスは、フライのシルエットや色ではなく、サイズによって明確に異なる反応を見せたのだ。
正直、フックサイズの違いだけでこれだけ結果に差が出るとは思わなかった。人気フィールド・荒雄川のニジマスならではのことかも知れない。C&Rで何度も痛い思いをしてきた彼らは、フライに対して非常にセレクティブになっているのだろう。
 しかし一方で荒雄川では、先行者の存在をあまり気にする必要がないこともわかった。
しかし一方で荒雄川では、先行者の存在をあまり気にする必要がないこともわかった。自分自身が奥まで立ち込んで散々叩いたそのポイントから、フライ交換をするだけでニジマスは入れ食いになったのだから。
写真のニジマスはこの川ではアベレージサイズだが、30cmはゆうに超える。太い流れに鍛えられた魚体はパワフルだ。
この魚には下流に走られてしまい、ようやくランディングできたのは、フッキングさせた位置から30m以上も下流だった。
(掲載日:2014年10月01日)
この記事の関連ページ



















