今月の一本 ~2014年3月 ガガンボ~(動画あり)|フライフィッシング データバンク
「今月の一本」2014年3月は、「ガガンボ」をピックアップし、動画とともに紹介
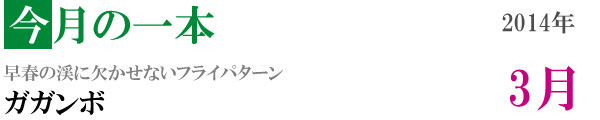
 3月。暦の上では春だが、フライフィッシングを楽しむ渓流域はまだまだ真冬。フライセレクトの主役はミッジであることが多い。
3月。暦の上では春だが、フライフィッシングを楽しむ渓流域はまだまだ真冬。フライセレクトの主役はミッジであることが多い。そうした中、この時期に多くの渓でユスリカとともに盛んにハッチするのがガガンボだ。水生昆虫の羽化が少ない早春、アマゴやイワナ・ヤマメにとってガガンボは極めて重要な捕食対象となっている。
意識するのはウスバガガンボ
渓流でよく見かけるのはウスバガガンボという種。3月初旬ごろからハッチする渓が多いようだ。この種が早春のフライフィッシングで意識しておくべきガガンボということになる。
ご存知のとおり、長い脚が特徴。一見すると「巨大な蚊」に見える。ボディはクリーム色系。体調は5mm前後。
メイフライと同様に水中羽化なのでイマージャーもよく渓魚に捕食される。
 CDCガガンボ(スペントウイング)
CDCガガンボ(スペントウイング)この類が、ガガンボ系フライで一番ポピュラーなフライパターンだろう。
#16~20くらいのフックにクリーム色やイエロー系のダビング材でボディをつくり、ハックルティップなどでスペントウイングをつくる。スペントウイングは、エアロドライウイング等のシンセティック素材を使う人も多いようだ。
このパターンのキモは、やはりレッグ。CDCで繊細な感じを表現している。このCDCは浮力や視認性を得るためのものではないので、オーバードレッシングにならないよう、タイイングに注意が必要だ。
このフライの場合、季節柄、緩い流れやプール状のポイントでのライズ狙いで使うことがほとんどになるだろう。そうした平坦な水面で使うので、視認性が問題になるケースは少ない。
浮力には難があるので釣上がりには全く向かない。
 CDCガガンボ(クローズドウイング)
CDCガガンボ(クローズドウイング)こちらは、前述のフライとはウイングの形状だけが違うフライパターン。写真でわかるとおり、ウイングを閉じてストレートにすっと伸びた状態をイミテートしたパターンだ。ウイングの素材は透明なポリ袋をカットしたもの。これをよじってボディ上部に取り付けている。
このフライの存在意義は、渓魚から見たシルエットがスペントウイングのフライとは全く異なる点にある。
1箇所のポイントでライズを狙い続けていると、渓魚がフライに飽きることがあり、シルエットの全く異なるフライを選択したくなることがある。そうした時、これがフライボックスにあると重宝する。なにしろガガンボ系で多様なシルエットのフライを用意していることは多くないのだから。
このパターンも浮力は弱いので、釣上がりには適さない。
CDCガガンボは「一発勝負」
実は、レッグにCDCを使ったガガンボフライには大きな欠点がある。
それは、水濡れに非常に弱いということと、耐久性がないということ。CDCが濡れてしまうと乾かすのが大変なのだ。繊細なファイバーが数本ついているだけなので、手荒に扱えば、すぐに千切れてしまう。1匹フッキングさせてしまえば、もうそのフライは交換するしかない。
そんな繊細なフライ。このライズは一発で仕留める、という時の「一発勝負」でティペットに結ぶのが良さそうだ
(掲載日:2014年03月09日)
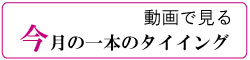
この記事の関連ページ


















