今月の一本 ~2016年5月 マダラニンフP~(動画あり)|フライフィッシング データバンク
「今月の一本」2016年5月は、「マダラニンフP」をピックアップし、動画とともに紹介
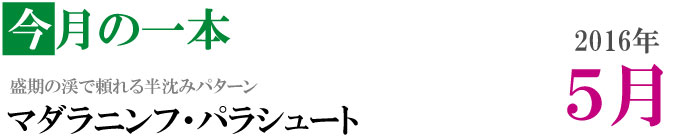
 5月というと、本格的に盛期を迎える渓が増えてくる。
5月というと、本格的に盛期を迎える渓が増えてくる。中旬ごろともなれば、北の地域や標高の高い山岳渓流でも雪代が治まりはじめ、いよいよフライフィッシングの一番楽しい季節の到来だ。
■釣り上がりシーズンの到来
春のフライフィッシングでは、ライズを見つけないことには釣りにならないという日も多かったが、5月になると、ライズはなくても流れをドライフライで叩いていけば、イワナもヤマメも姿を見せてくれることが多くなる。釣り上がりシーズンの到来というわけだ。
釣り上がりシーズンになると、パラシュート・タイプのドライフライの出番が増える。
 釣り上がりのフライフィッシングでは、波立った荒っぽい水面にフライを流すシーンが増えてくる。そうした水面では、波にもまれても沈まない浮力や安定した姿勢が得られるフライパターンが使いやすい。
釣り上がりのフライフィッシングでは、波立った荒っぽい水面にフライを流すシーンが増えてくる。そうした水面では、波にもまれても沈まない浮力や安定した姿勢が得られるフライパターンが使いやすい。パラシュート・タイプのフライはそうしたシーンにピッタリくるのだ。
■パラシュートのフローティングニンフ
今回取り上げたのは、そのパラシュート・タイプにタイイングしたフローティング・ニンフのフライパターンだ。
意識しているのは、オオマダラカゲロウなどマダラ系メイフライのニンフ。ボディ部分が水面直下を流れるハーフシンク(半沈み)パターンにタイイングしている。羽化直前。水面近くに浮いてきたニンフのイメージだ。
 といっても実際にこのフライを使う際は、春の繊細なマッチングザハッチのフライフィッシングと違って、特定の水生昆虫を意識する必要はあまりない。
といっても実際にこのフライを使う際は、春の繊細なマッチングザハッチのフライフィッシングと違って、特定の水生昆虫を意識する必要はあまりない。荒っぽい水面を流すことが多いこのフライパターンの場合、そうしたポイントで水面に関心を持っている渓魚は、神経質にフライを選別することは少ないからだ。
流速もそこそこにあるし、フラットでない水面の流下物は揺れ動く。そのような場所で捕食対象を待ち構えている渓魚たちには、フライをじっくり選別する余裕はないのだろう。あっさりとフライに飛びついてくれることが多い。
なので5月に限らず、イワナやヤマメの活性が高い状況なら、このパターンは秋の禁漁期まで活躍してくれる。なかなかに使い勝手の良いフライパターンなのだ。
 ■半沈みの利点
■半沈みの利点このパターンは、ボディ部分を水面下に沈むようにして使う。なので、ボディ部分をしっかり水で湿らせてからキャストする必要がある。
このようなハーフシンク(半沈み)タイプのフライには、大きな利点が2つある。
ナチュラルドリフト性能の高さと、渓魚からフライを見つけてもらいやすいという点だ。
「半沈み」というのは言葉を変えて表現すると、「ボディ部分が水面に突き刺さる」というイメージになる。突き刺さった状態で流れるので、フライが水面上で滑ったり転がったりしずらい。つまりナチュラルドリフトをさせやすいのだ。
もうひとつの利点、渓魚から見つけてもらいやすいというのは、当たり前だが、フライの一部が水面下を流れているので、渓魚からは見えやすいわけだ。フライ全体が水面上に浮いているよりも、かなり見つけやすいはずだ。

ある程度流速のあるポイントを狙うことが多くなる盛期の渓流では、フライが流れていることを、できるだけ早く魚に察知してもらいたい。
■タイイング
今回は色違い2種をタイイングした。濃い目のブラウンと薄いタンカラー。
ボディ部分はターキーバイオット。ソラックス部の下地にはオーストリッチを使った。ソラックス部のウイングケースはフェザントテールでつくっている。
インジケーターはエアロドライウイング。ピンクは白泡付近のポイントでも視認性がよい。テールはバーサテール。マダラ系のカゲロウを意識して3本にしているが、本数にこだわる必要はない。
フックはカーブドシャンクのものを使う。#12~#16くらいが適当だろう。
(掲載日:2016年05月24日)
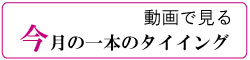
この記事の関連ページ


















