今月の一本 ~2016年12月 バイオットボディ・ニンフ~|フライフィッシング データバンク
「今月の一本」2016年12月は、「バイオットボディ・ニンフ」をピックアップし紹介
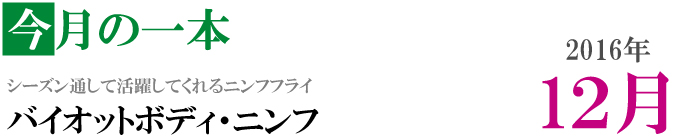
 ドライフライのフライフィッシングは確かに面白い。
ドライフライのフライフィッシングは確かに面白い。イワナやヤマメを水面におびき出し、水面上でフライを喰わせる。その瞬間、水面が割れる。飛沫があがる。
胸が高鳴る瞬間だ。
だがしかし、イワナもヤマメもドライフライにはどうにも反応してくれない日というのもある。そして、そういう日は決して少なくない。
そんな日もドライフライで一日通してしまうよ、という方もいるだろうが、フライフィッシングだって釣りなのだから、やはり魚と対面したい。
■渓魚との出会いが格段に向上する水面下
 釣れない日というのは、何を試してもやはりダメということもあるのだが、それでも狙いを水面上から水面下に変えるだけで、渓魚と出会える確立が格段に向上するのは間違いない。
釣れない日というのは、何を試してもやはりダメということもあるのだが、それでも狙いを水面上から水面下に変えるだけで、渓魚と出会える確立が格段に向上するのは間違いない。それは例えば、ライズがあって渓魚が水面に関心を持っているような時でも同じ。
盛んにライズがあるような状況では、当然ドライフライでの釣果が期待できる。
しかしそんなシーンで、水面下7cm~10cmほどの層にフライを沈めて流すと、さらに多くの釣果を手にすることができる、ということが多いものだ。

盛んにライズが見られるようなシーンでは、水面下を浮上しながら泳ぐ羽化寸前のニンフも、渓魚に捕食されているのだ。むしろ、水面上のダンなどよりも、水面下のニンフなどのほうが喰われている量は、圧倒的に多いらしい。
聞いた話だが、渓魚のうち、水面上のエサを喰う個体よりも、一生涯に一度たりとも水面上のエサを喰うことなく終わる個体のほうが多かった、という研究結果があるそうだ。
ドライフライのフライフィッシングというのは、ライズがあるような状況下でさえ、あまり効率的な釣りではないということなのかもしれない。
■ボディ部分はターキー・バイオット
 さて今回紹介するフライパターンは、見てのとおりメイフライニンフをイミテートしたもの。
さて今回紹介するフライパターンは、見てのとおりメイフライニンフをイミテートしたもの。ヘアーズイヤ・ニンフに似たシルエットだが、使っているフライマテリアルがそれとは異なる。
特徴的なのはボディ部分。ターキー・バイオットでつくっている。
魅力的なシマ模様をカンタンにつくりだすことができ、雰囲気のある仕上がりにすることができる。
タイイングの手間も少ないのが、うれしい。
今回は、白っぽいものとブラウン系のもの、2パターンをタイイングした。
 これは、渓流の底石の色によって使い分けるためだ。
これは、渓流の底石の色によって使い分けるためだ。底石が白っぽい場合は水生昆虫も白っぽく、底石が黒っぽければ水生昆虫も濃い色合いなのだ。
■ウイングケース
ウイングケースには定番のフェザントテールを使用。
ヘアーズイヤ・ニンフのウイングケースと全く同じつくり方をしている。
テールにはバーサテールを使用した。
今回のテールは3本にしたが、これを2本にしても4本にしても、釣果に影響することはないだろう。テールのカラーにも、こだわる必要はない。
■ソラックスにはオーストリッチを使う
 ソラックス部分に使っているのは、オーストリッチ。
ソラックス部分に使っているのは、オーストリッチ。ヘアーズイヤ・ニンフではこの部分にヘアーズイヤを使うのだが、これをオーストリッチにすることで、少し手間が省ける。
仕上げの段階でカットしながら整形し、分量を整えるといいだろう。
■使い方
ごく当たり前のニンフのフライパターンなので、使い方も一般的なニンフ・パターンと同じだ。インジケーターを使ってルースニングで釣るのが一般的だろう。
インジケーターからフライまでの距離は、当然、状況によって変える。前述のようなライズがあるような時は、10cm~20cmくらい。深場や底を狙いたい場合は、その層に合わせた距離をとることになる。
また、インジケーターを使用せずに、ウェットフライとして使ってみるのもありだ。
(掲載日:2016年12月28日)
この記事の関連ページ


















