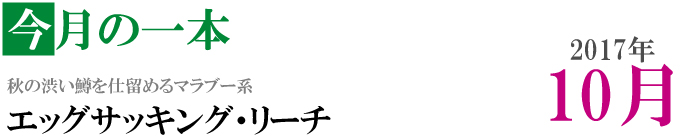
 産卵期が近づいたトラウトは、あまりエサを口にしなくなるといわれている。
産卵期が近づいたトラウトは、あまりエサを口にしなくなるといわれている。日本のトラウト類の多くが産卵活動をおこなう秋は、そうした意味ではトラウトフィッシングにはなかなか厳しい季節だ。
10月に入るとイワナやヤマメはほとんどのフィールドで禁漁になるが、これは秋の産卵活動を邪魔しないように、という意味合いが強い。
そうしたわけで、秋のフライフィッシングでメインターゲットとなるのはニジマスということが多い。
ニジマスは北米大陸が原産の外来魚なので日本の自然フィールドでの産卵活動を保護する必要がないうえ、そもそも日本の自然フィールドには定着しずらいとされる。

そうした背景もあって近年は、ニジマスの釣りに禁漁期間を設定しないフィールドや、在来トラウトが禁漁の秋から冬にかけてニジマス釣り場を設定するフィールドが増えている。
■魚卵をつつくヒル
さて今回は「エッグサッキング・リーチ」というフライパターンを少々アレンジしたものだ。
「エッグサッキング・リーチ」は、ヒルが魚卵をつつく様子をイミテートしたフライパターンとされている。
本当にヒルが魚卵をつついたりするものか知らないが、それなりにヒット率の高いフライパターンであることには違いない。

ニジマス狙いのフライパターンという印象を筆者は持っているが、それはイワナやヤマメを狙う際にこれを使っていないだけで、おそらくニジマス以外のトラウトにも有効なのだろうと思う。
■遺伝子を残す本能
一見アトラクター的な要素の強いフライパターンに見えるが、この類のフライパターンのヒット率の高さにはワケがある。
トラウト類には小さな球状のものをくわえる習性があるのだそうだ。
 自分のもの以外の魚卵を排除するための行動らしい。どうやら、自分の遺伝子が残る確立を高めようとする本能的な行動ということのようだ。
自分のもの以外の魚卵を排除するための行動らしい。どうやら、自分の遺伝子が残る確立を高めようとする本能的な行動ということのようだ。エサをあまり捕食しない産卵期でも、トラウトはこの行動をとる。いや、むしろ産卵期だからこそかもしれない。
渓流のエサ釣りではイクラは定番のエサ。フライフィッシングでは、エッグフライは「禁じ手」と自己規制するフライマンも多い。
それほど渓魚は魚卵を口にする、ということなのだろうか。
■フライ・タイイング
エッグサッキング・リーチは、単純なエッグフライではなく、「ヒルがつつく魚卵」という「ひとひねり」がされたフライパターンだ。
 今回のパターンはそれをさらに「ひとひねり」して、「魚卵をつつく小魚」というイメージを加えている。
今回のパターンはそれをさらに「ひとひねり」して、「魚卵をつつく小魚」というイメージを加えている。タイイングはいたって簡単。
一般的なマラブー・リーチの頭部分に赤いビーズがついている。マラブーの上にはカシミア・ゴートを乗せることで小魚感を演出した。フックは#8~#10くらい。
ちなみに、赤のビーズは手芸用品店で入手したものだ。
使用法は、一般的なマラブー・フライと同様。沈めてゆっくり引っ張る。
ところで勘違いされると困るのだがこのフライパターン、「ものすごく釣れる」というものではない。前述のとおり「それなりにヒット率の高い」というものだ。
筆者は他のパターンでの反応が鈍い日を中心に、ローテーションのひとつに組み込む、という使い方をしている。まあ、あまり過信をしないほうがいい。
もし「ものすごく釣れる」フライをお望みなら、赤のビーズだけをフックに取り付けた「イクラ・フライ」を試してみるのがいいだろう。
(掲載日:2017年10月26日)
この記事の関連ページ


















