今月の一本 2015年12月 アダムス系 4種|フライフィッシング データバンク
「今月の一本」2015年12月は、「アダムス系バリエーション・フライ」をピックアップ。
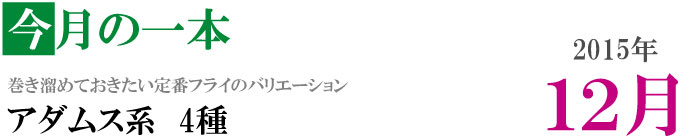
 アダムス。
アダムス。エルクヘアカディスなどと並んで、ドライフライのパターンとしては定番中の定番。バリエーションも数多い。
アダムス系のフライパターンはシーズンを通してフライボックスに常備している、というフライマンは多いはずだ。
■シーズン通して活躍するフライ
古い時代から使われているアダムス系のフライパターンが、現代のフライフィッシングにおいても活躍している理由のひとつとして、春先から晩秋まで、シーズンを通して活躍してくれるという点があげられるだろう。
メイフライ、カディス、テレストリアルまで「なんとなく」カバーしてしまうところが、季節を問わずに使える要因だ。
 ■パイロットフライに迷ったら
■パイロットフライに迷ったら様々な昆虫類に「なんとなくマッチする」という特徴は、パイロットフライとしての適正の高さを示している。
目立ったハッチがない時。多様な虫がハッチしていて何でも喰っている時。何を喰っているかわからない時。
アダムス系のフライは、そんなシーンで頼りになる。深く考えずにパイロットフライとしてティペットに結んでも、それなりに結果を出してくれる。
そうしたところが、アダムス系フライの使いやすさ。人気のゆえんなのだろう。
おおらかなフライフィッシングを楽しみたい時には、もってこいのフライパターンなのだ。
アダムス系フライのタイイング上での特徴は、ハックルにある。
グリズリーハックルとブラウン系ハックルをミックスして巻いている点だ。ミックスしたハックルとグレー系のボディの絶妙なカラーバランスが、様々な昆虫をカバーできる要因となっているのだろう。
シーズンを通して出番の多いアダムスのバリエーションパターン。
オフシーズンのうちに巻き溜めておきたいフライパターンのひとつということで、年末年始のこの時期に紹介しておくことにした。
■クラシック・スタンダード
 今回紹介している4種のうち、最もクラシックで本来のアダムス・パターンに近いのがこれ。
今回紹介している4種のうち、最もクラシックで本来のアダムス・パターンに近いのがこれ。このパターンはロングリーダー・ティペット使用時には使いづらい。しかしリーダー・ティペットが短めの時に使うと、抜群の実力を発揮することがある。
ハックルの下部をカットしないこのタイプのフライは、フライが水面から高く浮き、イワナやヤマメから見た時のシルエットが非常にあいまいになる。きっとイワナやヤマメは「よく見えないけど、なんか旨そうだな」というような印象を持つに違いない。
このフライパターンがよく釣れる理由が、そこにある。
河原のない小渓流や、ドリフトの距離が短い落差のある山岳渓流などでは、ロングリーダー・ティペットは扱いづらい。短いリーダー・システムで事足りることが多い。
そうしたロケーションでのパイロット・フライとして、現代のフライフィッシングでも通用するのが、このパターンというわけだ。
難点は水面での姿勢が安定しないこと。ロングリーダー・ティペット使用時には、水面で転がってしまう確立が高くなる。
 ■マラード・アダムス
■マラード・アダムス一方こちらは、ハックルの下部をバッサリとカットしたパターン。水面での姿勢安定度が格段に向上し、ロングリーダー・ティペットとの相性もいい。
ボディが水面にペタリと張り付く姿勢になるので、シルエットは渓魚からもクッキリと見えるはずだ。水面から高く浮くタイプと比べ、ナチュラルドリフト性能も格段に高くなる。日本の一般的な渓流で使いやすい現代的なパターンだ。
釣り上がりなどのブラインドのフライフィッシングでのパイロットフライとして重宝するが、様々な虫が一緒にハッチしている複合ハッチのシーンでは、ライズ狙いにも使える。
ウイングにはヘンハックルを使うのが一般的だと思うが、今回はマラードを使用している。このシマシマ模様が、釣れそうなイメージを演出する。釣れそうなイメージを持つフライは、自信を持ってティペットに結べるのがよい。
ところでマラード系ウイングのフライは、流れの色や光線の具合によっては視認性がよくないことがある。このパターンでもそれは同様だ
 ■CDCアダムス
■CDCアダムスこちらは、ウイングをCDCに替えたパターン。
視認性という点では、今回の4種の中で最も良くないのがこのパターンだろう。なので、荒っぽい水面のポイントでは使いづらい。波立っていないフラットな水面を、比較的長い距離、ドリフトさせたい場合にこのパターンをセレクトする。
そうしたポイントであれば、視認性が気になることはまずない。
CDCのカラーはナチュラルを使う。
フラットな水面では、渓魚はフライをじっくりと見てから捕食することができる。じっくり見られた場合に、最も虫っぽく見えるのがCDCナチュラルのウイングというわけだ。人間から見たときのルックスは地味なフライだが、渓魚からはこちらのほうが自然に見えるようだ。
カラーを変えれば視認性は格段に向上するが、それではCDCを使う意味はなくなる。このパターンでは、CDCのカラーはナチュラルにこだわりたい。
もちろんライズ狙いにも使える。
フラットな水面で、何を喰っているかわからないようなライズには、このパターンは頼りになる。あれこれ試行錯誤しながら捕食対象物を特定していくのも楽しいが、このパターンのように、深く考えずに結んでしまっても釣れるフライというのもまた、ありがたい。
 ■アダムス・パラシュート
■アダムス・パラシュート現代のフライフィッシングで使われているアダムス系フライの中で、最もポピュラーで人気のあるパターンがこのタイプだろう。
アダムスをパラシュート・タイプにアレンジしたフライパターンだ。
瀬での釣り上がりでパイロット・フライとして使うのにもってこいのフライ。どちらかといえば、魚の都合よりも人間の都合を優先させたパターンなのだが、なにしろ使い勝手が良い。
視認性と浮力がとても高い。波立った水面でもよく見えるし、よく浮く。
なにが喰われているか、などと考える必要がなく、とにかく流れに落とせば、渓魚が勝手に何かの虫と勘違いして飛びついてくれる。
耐久性が高いので、フライを結び替える頻度も少なくて済む。一旦濡れてしまっても、渇きが早い。
とにかく便利でおおらかなフライパターンなのだ。
■タイイング
今回の4種は、タイイング上で特に注意すべきことはない。ごく一般的なフライタイイングの手法で問題なく巻ける。
テールは、バーサテールのブラウンとブルーダンをミックスしている。他のマテリアルと比べ、ちぎれにい。耐久性が高いのだ。ボディはグレー系のダビング材。材質はこだわる必要はないだろう。
フックサイズは、#12~#18くらい。各サイズを巻いておくことで、様々な虫に対応させられる。写真のパターンでは、AXISCOのAFB-305を使用。このフライは、ショートシャンクのフックが適している。
(掲載日:2015年12月29日)
この記事の関連ページ


















