今月の一本 ~2017年6月 FTクロカワムシ~|フライフィッシング データバンク
「今月の一本」2017年6月は、「フローティング・クロカワムシ」をピックアップし紹介
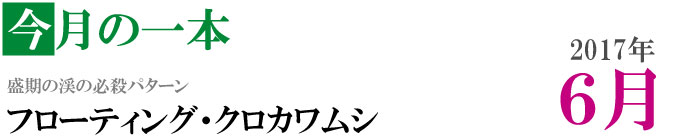
 6月に入るとフライフィッシングの最盛期を迎える渓流が多くなる。
6月に入るとフライフィッシングの最盛期を迎える渓流が多くなる。雪代の入る渓流でも水量が落ち着いて、イワナもヤマメも気前よくドライフライに飛び出してくれる日が増える。
フライセレクトにも神経質にならずにすむ。
渓魚の食欲が旺盛なこの時期、イワナもヤマメも流れてくる昆虫を選ばずに喰う。繊細だった春のフライフィッシングと違って、ずいぶんおおらかな釣りができるようになるのだ。
とはいえ、その中でも「よく釣れる」フライパターンというのは、やはり存在する。
今回紹介するフローティング・クロカワムシも、そんな「よく釣れる」フライパターンのひとつだ。

■良型渓魚に好反応
今シーズン、筆者は雪代明けの5月下旬からこのフライパターンを使い始めたが、イワナもヤマメもこのパターンには好反応だ。尺イワナにも遊んでもらえた。
季節柄、「このフライだからこそ釣れた」というケースは多くないのだろうが、感覚的には他のフライパターンよりもグッドサイズの渓魚に反応がよく、フッキング率も高いように感じている。
■クロカワムシ
さて、クロカワムシはご存知のとおりヒゲナガカワトビケラの幼虫だ。
 エサ釣りの世界では良型渓魚のエサとして重宝されている。
エサ釣りの世界では良型渓魚のエサとして重宝されている。渓流の流れの中に転がる石をひっくり返すと、石の表面に小石を集めてつくられた巣を見つけることができる。その中にいる少々グロテスクな風貌の川虫がクロカワムシだ。
もっとも、このフライパターンで釣れてくるイワナやヤマメが、このフライを「クロカワムシだ」と認識して喰ったのかという点は、かなり疑わしいと思っている。
おそらく、「なにやら喰えそうな虫が流れてきた」という程度ではないだろうか。
■渓魚にアピールする何か
 それでもこのフライがよく釣れるということは、渓魚にアピールする何かが備わっているということなのだろう。
それでもこのフライがよく釣れるということは、渓魚にアピールする何かが備わっているということなのだろう。それはボディの体節の感じかもしれない。ボディの微妙な透明感かもしれない。パートリッジでつくったレッグが醸しだす虫っぽさなのかもしれない。
あるいは、それらの総合的なバランスが優れているのだろうか。
いずれにせよ、5月下旬から禁漁までの期間、大活躍してくれるフライパターンであることには違いない。盛期の渓流フライフィッシングでは頼りになるフライなのだ。
■ボディはVINYL RIB(ビニール・リブ)というマテリアル
 このパターンのボディ部分は、VINYL RIB(ビニール・リブ)というフライマテリアルでつくっている。カラーはオリーブ。
このパターンのボディ部分は、VINYL RIB(ビニール・リブ)というフライマテリアルでつくっている。カラーはオリーブ。似た素材であれば、VINYL RIBにこだわる必要はない。
体節を簡単に表現できて透明感がある。耐久性も魅力的だ。どれだけ釣っても千切れたりすることがないのはウレシイ。
■ラムズウール
このフライのボディ部分は重いので、ウイング・ポストでしっかりと浮力を確保しないと簡単に沈んでしまう。
そのウイング・ポストにはラムズウールを使用した。空気を多く抱える素材なので、高い浮力を実現できる。

カラーはライトダン。ラムズウールには様々な色合いが用意されているが、やはり落ち着いた色合いのものを使うほうが、渓魚の反応がよい。
■タイイング
タイイングでは、まずボディ部分を巻いてしまう。
その後にラムズウールでウイングポストをつくる。
続いてソラックス部分を巻くが、今回はその部分をフェザントテールでタイイングしている。ここはダビング材でタイイングしても差し支えない。
さらにパートリッジでレッグをつくる。ソラックス部の下面に適量。今回はボディ部分より長めにつくったが、もう少し短くても釣れ具合に影響はないように感じている。
最後にパラシュート・ハックルを巻く。コックネックのグリズリーが似合うが、茶系の色合いを使ってもよいだろう。
フックは、がまかつC14-BV。#12前後のサイズを使う。
(掲載日:2017年06月28日)
この記事の関連ページ


















