今月の一本 ~2015年3月 ガガンボイマージャーパラシュート~(動画あり)|フライフィッシング データバンク
「今月の一本」2015年3月は、「ガガンボイマージャーパラシュート」をピックアップし、動画とともに紹介
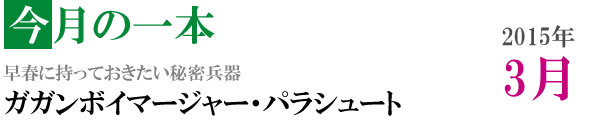
 3月に入ると全国の多くの渓流で、イワナ・ヤマメ・アマゴの釣りが解禁となる。フライフィッシング・シーズンもいよいよ本格的なスタートを迎えるというわけだ。
3月に入ると全国の多くの渓流で、イワナ・ヤマメ・アマゴの釣りが解禁となる。フライフィッシング・シーズンもいよいよ本格的なスタートを迎えるというわけだ。シーズンの初釣行は毎年3月、というフライマンは少なくないだろう。
選択肢の少ない3月
とはいえ、一部の特別なフィールドを除けば、3月の渓流はまだまだ冬の延長にあることが多い。この季節にハッチ(羽化)をする水生昆虫もごく限られた種だけで、ハッチの主役は2月に引き続きミッジという場合がほとんどだろう。それに混じってストーンフライ(カワゲラ)やクレーンフライ(ガガンボ)のハッチが多くの渓流で見られるようになるのが3月である。
3月も下旬くらいになるとようやくコカゲロウのハッチが目につくようになってくるが、それも関東以南の渓の話だろう。
 したがって3月のフライフィッシングで用意しておくべきフライパターンというのは、実はあまり多くない。そういう意味ではフライボックスにとっては、3月は少々寂しい季節なのかもしれない
したがって3月のフライフィッシングで用意しておくべきフライパターンというのは、実はあまり多くない。そういう意味ではフライボックスにとっては、3月は少々寂しい季節なのかもしれないもっとも、これはドライフライに限定した話であって、ニンフなどを沈めるフライフィッシングも考えに入れるとなれば、フライセレクトの選択肢は飛躍的に広がる。
渓魚たちはこの時期でも、水面下では様々な種類のエサを捕食しているのだ。
水面直下のパターン
さて今回紹介するフライパターンは、ボディ部が水面に突き刺さって流れるドライフライ。水面直下のパターンで、ガガンボを意識したフライだ。
ガガンボの生息域は中流域。里川のエリアということになる。上流域の山岳渓流エリアでは、あまり見かける種ではない。水温の上がりやすい陽だまりの緩い瀬やプール状のポイントで、お昼前後にハッチしていることが多い。
 瀬にせよプールにせよ、比較的浅い流れでハッチする。
瀬にせよプールにせよ、比較的浅い流れでハッチする。実のところ、ガガンボがまとまって大量に流下してくるという状況は、筆者はこれまで見たことがない。ガガンボに対するライズも散発のものばかりで、安定してまとまったライズには、これまでは遭遇したことがない。
ところが、そうしたライズの少ない状況下でも、渓魚のストマックの中にはたくさんのガガンボが入っっていたということは、意外に多くのフライマンが経験しているのではないだろうか。
このような場合、渓魚は水面上ではなく水面下のガガンボを多く捕食していたということなのだろうと、筆者は考えている。
 ガガンボはメイフライ(カゲロウ)と同様に水中で羽化をする。その羽化途中の状態をイマージャーと呼ぶわけだが、イマージャーはとても無防備な状態なので、渓魚にとっては非常に都合のよい捕食対象なのだ。
ガガンボはメイフライ(カゲロウ)と同様に水中で羽化をする。その羽化途中の状態をイマージャーと呼ぶわけだが、イマージャーはとても無防備な状態なので、渓魚にとっては非常に都合のよい捕食対象なのだ。このフライパターンは、そのイマージャーを意識している。ボディ部分が水面下に沈むデザインに仕上げているのには、そうした理由からというわけである。
ボディはグースバイオットで
今回タイイングしたフライは、そのボディ部分にグースバイオットを使ってみた。
このマテリアルの最大の特徴は、絶妙な雰囲気を持った縞模様を表現できるところにある。この縞模様が、ガガンボイマージャーの体節を表現している。ガガンボのイマージャーは黄色っぽい色合いなので、グースバイオットのカラーはイエローダンのものを使っている。
ハックルにはコックネックの毛足の長い部分を使用。カラーはブルーダン。この部分はガガンボの足を表現しているので、量が多いと不自然。はらりと1回転ほど巻くだけにしておく。
フックは細軸のカードドシャンク。写真のパターンに使ったフックはバリバスの2210。ティムコTMC212Yでも同様のシルエットをつくることができる。
(掲載日:2015年03月01日)
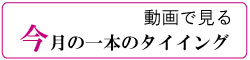
この記事の関連ページ


















