今月の一本 ~2014年8月 CDCコーチマン~(動画あり)|フライフィッシング データバンク
「今月の一本」2014年8月は、「CDCコーチマン」をピックアップし、動画とともに紹介
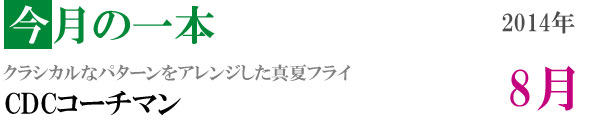
 今回とりあげるフライパターンは、ロイヤルコーチマンをアレンジしたテレストリアルフライ。
今回とりあげるフライパターンは、ロイヤルコーチマンをアレンジしたテレストリアルフライ。ロイヤルコーチマンは、世界中のフライマンに愛用されているフライパターンで、日本では真夏の渓流で使うテレストリアルフライとしてティペットの先に結ばれることが多い。
英王室の御者のパターンが原型
ロイヤルコーチマンの原型は、英国王室の御者(馬車を操る専門スタッフ)だったトム・ボスワース氏によって1830年に考案されたフライパターン。「コーチマン(Coachman)」とは御者のことを指す言葉だ。
ボスワース氏は、ビクトリア女王などの馬車を走らせたエリート御者だが、その一方で華麗なキャスティングを披露するフライフィッシングの名手でもあった。
そのパターンがアメリカでアレンジされたものがロイヤルコーチマンだ。
「ロイヤルコーチマン(王室の御者)」という名は、Orvis社の創業者であるC.F.Orvis氏が命名したらしい。
このフライパターンは、その後も様々なバリエーションが発表されながら現在に至っている。
 渇水や反応の渋い時に
渇水や反応の渋い時にさて、今回のパターンは主に真夏の山岳渓流でのフライフィッシングで使うことを想定している。
夏のフライは視認性の良いポリウイングにハックルをびっしりと巻いたパラシュートタイプのドライフライが主役になることが多い。が、渇水気味の流れや平坦なポイントではCDCのパターンが欲しくなる。また、イワナやヤマメの反応が渋い時には、パラシュート以外のシルエットを試したくなる。
そんなシーンで結ぶのが、このフライパターンだ。
CDCウイングの半沈みパターンにアレンジ
本来のロイヤルコーチマンは、白いダッククイルの2枚ウイングがとても美しいのだが、今回のパターンでは、ウイングをそっくりCDCに置き換えている。色はナチュラルが良いが、淡い色合いのCDCを使うと視認性が向上し、小さなサイズにタイイングしてもよく見える。渓魚の反応という点では、ナチュラルのほうがが勝る。
ボディ部分は水面下に沈む「ハーフシンク(半沈み)」タイプに仕上げている。そのため、ロイヤルコーチマンの特徴でもあるゴールデンフェザントティペットのテールは、取り付けていない。
 華麗で美しいロイヤルコーチマンが徐々に変っていって「王室の御者」から「駅馬車の御者」くらいまで地味なデザインになってきた。
華麗で美しいロイヤルコーチマンが徐々に変っていって「王室の御者」から「駅馬車の御者」くらいまで地味なデザインになってきた。半沈みにする理由は、渓魚の反応が渋い時にはボディ部分が水面下にあるパターンが頼りになること。また、ボディ部が水面に突き刺さっていることで、フライが水面で滑らない。つまり、ナチュラルドリフト性能が高いという理由もある。
フックはカーブドシャンクのものを使用する。
お尻とソラックスはピーコックハール。ボディ真ん中の赤い部分はフロスだ。
ハックルの上下はカットする
写真のパターンではハックルにブラックのコックネックを使用しているが、これはブラウンでもよい。本来のロイヤルコーチマンはブラウンハックルが王道だ。
ただしロイヤルコーチマンと違い、今回のパターンではハックルの上下をカットする。下方のハックルがカットされていないと、着水時にフライが高く浮いてしまい、ボディ部分がすっきりと沈まないからだ。
 上方のハックルもカットするのは、ウイングのCDCを寝かせ気味に取り付けたいため。
上方のハックルもカットするのは、ウイングのCDCを寝かせ気味に取り付けたいため。ロングティペットでキャストする際にフライがクルクルと回転してしまわないようにする目的もある。
今年もこのフライは活躍している
フックサイズは水量の乏しい流れでは#18。平水なら#16~#14。増水気味の時には#12くらい。
あえてマッチする昆虫を挙げるとすれば、ムネアカオオアリ。しかしこのフライはロイヤルコーチマン同様、特定昆虫のイミテートでなく、ファジーなパターンと考えるべきだろう。
今シーズンもこのフライが活躍するシーンがあった。
7月後半の秋田の渓と、8月前半の中央アルプスの渓。両方とも減水気味、日差しが強く蒸し暑い流れでのフライフィッシングになった。
どちらのフィールドからも、ネイティブで美しいイワナ達が、このフライパターンに元気よく飛び出してくれた。
(掲載日:2014年08月07日)
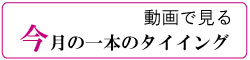
この記事の関連ページ


















