【フライタイイング】ビニールリブ&パートリッジ(動画あり)|フライフィッシング データバンク
「今月の一本」2017年7月は、「VR&P」をピックアップし、動画とともに紹介
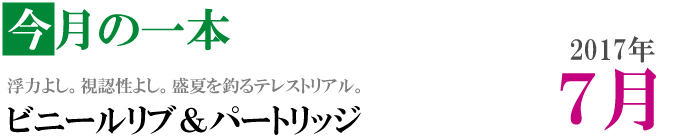
 今回のフライパターンは、前回(2017年6月)「今月の一本」で紹介したフローティング・クロカワムシをテレストリアル風にアレンジしたもの。
今回のフライパターンは、前回(2017年6月)「今月の一本」で紹介したフローティング・クロカワムシをテレストリアル風にアレンジしたもの。前回と同様にビニールリブとパートリッジを組み合わせたドライフライだ。テレストリアル・シーズンのはじまる6月中旬から禁漁までの渓流フライフィッシングで活躍してくれる。
ただしその季節でも、例えば小さな羽アリなどのフライパターンでないと良い結果を得られないようなこともある。今回のフライパターンはそうした繊細なフライフィッシングには適さない。
このフライパターンは小型にタイイングすることが難しいからだ。
 ビニールリブというフライマテリアルでつくるボディ部分は、比較的ボリューム感のある仕上がりになる。そのため、小さなフックには不釣合いなのだ。
ビニールリブというフライマテリアルでつくるボディ部分は、比較的ボリューム感のある仕上がりになる。そのため、小さなフックには不釣合いなのだ。さらにこのビニールリブは、重めのマテリアルだ。重いことでボディ部分がスッと水面を割って沈んでくれる。
水面上に浮くのは、パラシュート・ポスト(インジケーター)とハックル。しっかり浮かすためには、パラシュート・ポストも大きめに作る必要がある。となると、やはり小さいフライフックではバランスが悪くなってしまう、というわけだ。
適したフックサイズは、#12前後。#14が、ギリギリこのパターンをタイイングできるフックサイズだろう。
■「何だかわからないが虫っぽい」ドライフライ
 さて、このフライパターンは特定の昆虫を模したものではない。何だかわからないが、とにかく虫っぽい、というファジーなドライフライだ。
さて、このフライパターンは特定の昆虫を模したものではない。何だかわからないが、とにかく虫っぽい、というファジーなドライフライだ。テレストリアル(陸生昆虫)を意識したつくりにはなっているが、実際にはカディス・ピューパなどの水生昆虫に、イワナやヤマメからは見えているかもしれない。
そんなフライなので、これを使うシーンは、渓魚が特定の捕食対象を偏食していない時、ということになる。
特に6月中旬から7月いっぱいにかけての山岳渓流では、そうしたシーンが多い。流れてくる虫なら選ばずに喰う。偏食しない。
その時期の山岳渓流では、特定の虫が集中的に流下してくることは稀なので、当然といえば当然のことだ。
そんな日のフライセレクトは、「とにかく虫っぽい」ということがとても重要になってくる。
■耐久性が高く壊れない
 このフライパターンの良いところのひとつとして、耐久性の高さがあげられる。
このフライパターンの良いところのひとつとして、耐久性の高さがあげられる。前述のような最盛期の山岳渓流では、キャストするポイントごとに渓魚がフライに飛び出してくる、というような日もある。
そんな時に、数匹釣っただけでフライが壊れてしまう、ということでは、イライラしてしまう。
CDC系など、一匹釣った後にフライを再生させるための処理に時間のかかるフライパターンも、同様にストレスになる。
それに対して、今回のフライパターンは耐久性が高く壊れづらい。ボディ部分のビニールリブの強度が高いためだ。
パラシュート・ポストに使っているラムズ・ウールも、CDCと比べると釣った後の処理が早い。

そんな「手返しの良さ」が、このフライの魅力のひとつなのだ。
■タイイング
このパターンのフライタイイングをする上で、特に難しいことはない。風変わりなテクニックも不要。
簡単にタイイングできるが、詳細は動画で確認してほしい。
ボディ部分のビニール・リブのカラーはオリーブ。
パラシュート・ポストに使っているラムズ・ウールのカラーは、ライトダン。
ラムズ・ウールは空気をたくさん抱え込んでくれるので浮力が高い。視認性もよい。
ソラックス部分にはピーコック。ハール部分でもソード部分でもよい。
ハックルは黒のコックネック。
フライフックはカーブド・シャンクを使う。今回は、がまかつC14-BVにタイイングしている。
(掲載日:2017年07月25日)
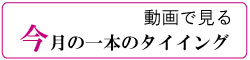
この記事の関連ページ


















